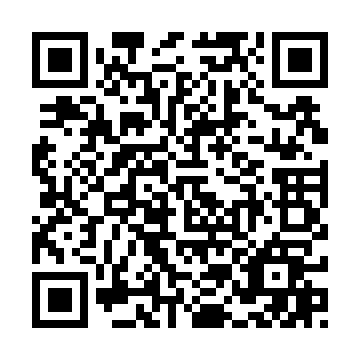今盛んに「
生産性向上」とか「
業務効率化」という一人ひとりのGDP底上げが言われています。
日本は他の国に比べて低いから、とりわけ長野はそれが低いとされています。
そこを改善できるのではないかという、
伸びしろの可能性があるわけです。
ただ、地方に住んでいると、そこには3つの壁の存在を感じるんです。
1つ目は、もちろん
個人によるもの。日本は他の先進国に比べ、労働者だったとしても経営者になれる非常に貴重な国。
妻の住むスペインはその辺のボーダーラインがあって、妻の父は能力があっても最後まで労働者でした。
だから、能力を高めればそれなりの地位を自ら得ることができる。だから、会議所も盛んに勧めます。
この先もどんな人生になるか分からないですしね。
2つ目は、
職人気質である点。その道のスペシャリストになることには非常に優れているんですが、周りはついてこれない。この日本の多様性はまさにこれが言える気がします。下諏訪出身で東京でソフトウェア開発をしている人も言ってました。日本はシステムのカスタマイズがすごいと。そのシステムに環境を合わせていく外国の一方で、日本はその環境にシステムを合わせていこうとする需要があります。ガラパゴス化する理由ですね。多消費文化による経済が活発なのもこれが言えるんではないかと思います。日本の良いところでもあるので、複雑です。
3つ目。
慣例とか慣習、目上の存在。これは地方において、この人口減少社会において一番の課題になるのではないかと思います。
形式を維持するために、無駄なことをあえてしなくてはいけない。「これやらなくても良いんじゃない?」とか「自分ここにいなくても良いんじゃない?」はご法度。
それをやること、そこにいることが、どんなに無駄なことでも大事なんですから!なぜなら、今までそうやってきたから。続けること、続くことが財産となってきた日本では、譲れない部分です。
また、最近の業務効率化を政府でしきりに言っている割には、軽減税率制度みたいなそれを阻むような法律作っちゃう。下の人間は、押しつけをくらいます。みんなサラリーマンならいいんですよ。地元の個人事業主からはブーイングしか聞こえてきません笑。私は、個人的に将来もっと差を作る前哨戦と捉え、この仕組みに慣れるためのステップとする前向きな想いもジレンマとしてあります。
我々個人レベルで変えられるとしたら、1でしょうか。
下諏訪商工会議所では、できるかぎりその「生産性向上」「業務効率化」に挑戦していきます。