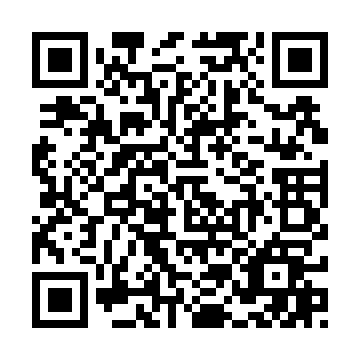6月よりQRコード決済の導入推進をしていきます。
現在の状況を整理すると、
ただし、注意が必要で、あくまでも対象事業者となったからと言って、セブンイレブンなどのコンビニ等大手量販店のバーコード決済が可能になっただけで、小規模事業者の静的な決済(※こちらを参照)には対象となっておらず、別途申し込みが必要です。
これはあくまでもうわさレベルですが、PayPayはお金をかけて導入推進を図ってきたわけで、それを今さら相乗りするような形で統一されてしまうと、PayPayとしてのメリットが失われてしまいます。
この統一規格の勧め甲斐の点から言えばちょっとぬか喜びですが、「まあ、しょうがない」です。
ただ、いずれは今現状の携帯電話の変遷から言えば、この先どうなるかはわかりません。
また、実はQRコード決済にも3種類あります。
1.電子マネー型の前払い入金型。
2.デビットカード的な即時決済型。
3.クレジッドカード的な後払い型。
実際にアプリを使っている方ならわかると思いますが、電子マネーのようにお金を銀行からチャージして使うタイプ。
もう一つはQRコード決済のアプリを経由して銀行から払うタイプ。
さらにもう一つは、クレジッドカードを登録してチャージまたは払うタイプ。
同じQRコード決済でもお金として出ていくタイミングが違います。もちろん、受け取る事業者も変わってきます。
共通して言える便利さとしては、「スマホさえあれば生きていける」です。
先日、とある花屋の社長さんが、電車で大阪に行く時に財布忘れてでかけちゃったんだそう。1泊2日でも、スマホだけですべてまかなえたという話。
例えばですよ、QRコード決済できる店が近くなかったとしても、
「ごめん、ちょっと小銭ないからもらってもいい?PayPayでお金払うからさ」
個人間でのお金のやり取りもできちゃうんですから。※職員間で実験済w
以前、ロンドンに住んでいた時に、バークレー銀行というイギリスでは大きな銀行の口座開設をした際、デビット機能のついたキャッシュカードを受け取りました。日本ではクレジッドカードに慣れていた人間にとっては、そのデビットカードで買い物ができる仕組みは非常に便利でした。滞在期間も、ポンドでもらう給料も決まっていた私は、その収支管理は徹底しなくてはならず、後払いは怖かったんです。
なぜ日本でデビットカードは普及しなかったんでしょう。今の銀行はここに致命的なミスがあったように感じます。きっとこれを普及しておけば、銀行としての今のQRコード決済への移行も相当スムーズであったでしょうに。