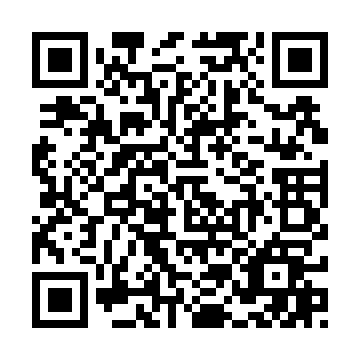時々悩むときがあります。
実力主義とか、実績主義とか、言われていた時代もありました。今でも言われています。
多く結果を残す人ほど恩恵を受ける。それが一番だ、と。
独身時代の私であったら、「いやその通り。自分も結果を残せるようにがんばる」ってなっていたと思います。
でも、多様化する時代。ダイバーシティの時代。日本は多様化に加えて貧富の二極化も進んでいます。
私も外国人の妻がいて、子供を育ててると人より不自由を感じることが多々あります。自分で選んだし、自業自得だよ、と言われたらそのとおりなんです。
でもそれって、独身の人もいるし、ご自身が、もしくはご家族が障害を抱えている人もいるし、いろんな人います。
だから、それぞれが自分の実力に応じてがんばる、まさにそれが「ヒーロー主義」。会議所の職員であると別に自分の収入は増えないけど、得意分野を活かして他の職員よりがんばろうとするときがまさにそれ。
スパイダーマンだって、スーパーマンだって、スーパーパワーがあるからこそそれを活かす義務が生じ、その葛藤をよく描いています。ヒーローであることの恩恵がないから。「普通の生活送りたい!」って。
この2つの主義とうまく付き合っていかなくてはいけません。